第22回 オグリキャップ
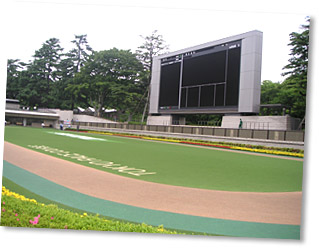 二十歳代の後半を過ぎた頃から僕は毎週のように競馬場へと出掛けるようになっていた。それが自分の唯一の生業となっていた時期だった。僕の周りにはいつも競馬好きの友人たちが屯っていた。G1が行われる日などは良い指定席を何とか確保する為に、長時間真夜中の府中に仲間たちと並んだことなどもあった。それくらいに「競馬」が熱を帯びていた。そしてそのブームの中心には稀代のスーパーホースの存在があった。折りしも国中が日本経済の活性化による好景気に包まれ、誰もが浮かれていた時代だった。 二十歳代の後半を過ぎた頃から僕は毎週のように競馬場へと出掛けるようになっていた。それが自分の唯一の生業となっていた時期だった。僕の周りにはいつも競馬好きの友人たちが屯っていた。G1が行われる日などは良い指定席を何とか確保する為に、長時間真夜中の府中に仲間たちと並んだことなどもあった。それくらいに「競馬」が熱を帯びていた。そしてそのブームの中心には稀代のスーパーホースの存在があった。折りしも国中が日本経済の活性化による好景気に包まれ、誰もが浮かれていた時代だった。
1985年3月27日、北海道三石郡三石歌笛の稲葉牧場で、父ダンシングキャップ、母ホワイトナルビーの間に一頭の芦毛の牡馬が生まれた。通常、馬は生まれてすぐに立ち上がる。それは厳しい自然の中で外敵から身を守る為に備わっている本能。しかしその馬は誕生から一日かかっても立ち上がれなかったという。将来を案じた牧場長は自らがミルクを与え、その仔馬が元気に育つことを願い、「ハツラツ」という幼名を付けた。やがてハツラツは笠松の馬主であった小栗孝一氏の所有馬となり、笠松競馬場所属の鷲見調教師の下で競走馬としてのデビューを迎えることとなる。競走馬名は冠名となる馬主の苗字と父の名前から「オグリキャップ」と名付けられた。
オグリキャップは産まれた時のひ弱さがまるで嘘のように、デビュー時から周囲にその非凡な能力を強く印象付けた。快進撃が続いてゆくと「公営笠松に怪物アリ」と中央競馬ファンの間でも囁かれるようになっていった。しかし公営競馬所属の競走馬が中央競馬で自由にレースを選び走ることは出来ない。そうなる為には中央競馬の所属になることが必要であり、まずその為には馬主が中央競馬会の承認を受けていなければならなかった。残念ながら小栗氏はそれを受けていなかった。オグリキャップに競走馬としての大きな可能性を感じていた小栗氏は、ファンの願いを叶えるべく、中央競馬の資格を持った馬主にオグリキャップを譲渡することを決断した。その夢と願いとは、ただひとつ『日本一の競走馬になること』だった。
中央競馬初見参は1988年3月6日、阪神競馬場で行われた「ペガサスステークス」だった。鳴り物入りで登場した「公営の雄」に対して観客や評論家は半信半疑だったが、結果は三馬身差をつける大楽勝。オグリキャップはまるで周囲の雑音を嘲笑うかのように同世代のライバルに後塵を浴びせた。ここから彼の快進撃は始まる。連勝を重ねてゆくオグリキャップに対するファンたちの興味は『もしダービーに出走したら勝てるのか?』ということに集中した。しかし彼はダービーに出走することは出来なかった。それは出走の為に必要な事前のクラシック登録がなされていなかったからだ。
「血統こそ競馬である」と言い切る評論家は多い。それほどまでに競馬は血統が重要視されるスポーツなのだ。クラシックレースへの登録をするかしないかということは、血統が大きな目安になっている。ではオグリキャップの血筋はどうであるかと云えば、お世辞にもそれは素晴らしいものとは云いがたい。しかし彼のように一流ではない血脈から名馬が生まれるということは、稀にではあるが昔からあったことだ。「血統」が優遇され、成功を収めてゆく、といったことはいつの時代、どの社会においても王道として存在している。だがこの時代においては、空前の好景気を背景に、正当な血統になくとも成功者と成り得る、そんな気運が社会に充満していた。アウトローである彼が勝ち続け、昇り詰めてゆく姿に人々は希望を感じ、夢を膨らませ、そして大いなる勇気や活力を得ていたのだ。
この時期の日本経済が「バブル期」と一般的に呼ばれるようになったのは、それが崩壊した後のこと。この頃、僕はちょうど我が人生最大の「混迷期」にあった。今から思えば、生活そのものが非常にバブリーなものだった。しかしそうしたことが自分の中でまともに整理し理解出来るようになるのは、実際にそんな生活から抜け出してからの話だ。『こんな空しい生活を続けていても意味は無い』そう思いつつも、激しく貪り続ける過剰な消費経済の大波に揉まれるままに、僕は希望の見えない自分の未来に焦り、喘ぎながらも出口を見つけられず、自分自身を消耗し続けた。生き方を変えることが出来ない、意気地なしのあの日の僕は、新たな時代の訪れによって自分が変えられることを何もせずにただ待っているだけだった。
快進撃を続けてゆくオグリキャップの人気はやがてアイドル化し、彼の走りに熱狂する人々の行動はもはや社会現象にまでなっていった。彼は人々の夢を乗せ、ひたすら激走を続ける。クラシック三冠レースには出走出来なかったものの、その年の暮れのグランプリではついに宿敵タマモクロスを破り、念願の「日本一」に輝き、名実共に現役最強馬となった。しかしその短い間に登り詰めてしまったことの反動は大きかった。

翌春、オグリキャップは脚部に故障を発生し、長期の休養を余儀なくさせられる。しかし秋には戦線に復帰、G2を連勝、そして目標にしていた「天皇賞(秋)」を迎えた。宿敵、タマモクロス号が既に引退していたということもあり、誰もが彼の優勝を強く感じていた。戦前に発表されていた「天皇賞(秋)」以降の出走プランは「ジャパンカップ」「有馬記念」という厳しいものだったが、多くの競馬ファンは「すべてオグリが勝つ」と考えていた。しかしその初戦「天皇賞(秋)」で彼はファンやオーナーサイドの期待に応えられなかった。まさかの二着。急遽、出走プランが変更された。それは競馬の常識では到底考えられない計画であり誰もが仰天した。世界一を決める大一番「ジャパンカップ」の一週前に、G1「マイルチャンピオンシップ」に出走させるというのだ。誰がそうさせるのかはよく知らない。が、オグリキャップのファンは望んではいなかった。何故なら、そんなことをすれば骨折し、命さえ危険に晒してしまう可能性が増大すると誰もが知っていたからだ。
しかしそんな心配を他所にオグリキャップは激走を続けた。急遽参戦をした「マイルチャンピオンシップ」では、直線入り口で一旦は抜かれ離されはするものの、ゴール直前では差し返して優勝。レースで彼の背に乗っていた南井騎手は彼のその根性に男泣きをした。続く連闘となる翌週の「ジャパンカップ」では東京競馬場の長い直線で叩き合いのマッチレースとなり、写真判定の末に二着に敗れるもその走破タイムは世界タイレコードというものだった。『もう充分だよ。君は本当によく頑張ったよ』。僕にはその感動の涙を止めることが出来なかった。彼が何を思い、何を望んだのかは解らない。けれど僕には、ひたむきに走り続ける彼の姿に自分に欠けている何かを見ているような気がした。
「有馬記念」での彼はレース前からいつもとは何かが違っていた。彼は闘志をまったく見せることなく五着でレースを終えた。『きっと疲れているのだろう』そんな声が多く聞こえてきた。その後もオグリキャップは現役を続けた。鞍上に天才武豊を迎えた春のマイルG1「安田記念」でこそ優勝したものの、その後は無残な惨敗を繰り返した。その頃になると多くの評論家が『もう往年の体ではない』と口にするようになった。そのげっそりとした筋肉は、素人目にも悲しいものだった。全盛期のオグリキャップにはその隆々とした筋肉に加え、さらに突出している点があった。それは彼が持つ「激しい気性」。近寄る者の指を本気で噛み千切ろうとする荒々しさを持ち、その顔は常に険しかったが、この頃には既にそんな気性はすっかりと影を潜め、表情はまるで別馬のようになっていた。
そして迎えたラストラン「有馬記念」。そこで奇跡は起きた。武豊と再びコンビを組んだ彼はもう一度だけ激走を見せたのだ。驚きとどよめき、そして皆が泣いていた。「オグリ!オグリ!」と呼ぶ大歓声が競馬場に響き渡った。それは命を懸けて走り、与え続けてくれた勇気と感動に対する感謝の思い、そのものだった。そんな皆の思いこそが彼の闘志を燃やし、奇跡の糸を手繰り寄せたのかもしれない。走りの中で彼が背に乗せていたのはジョッキーだけではなかったのだという思いがした。
やがて日本のバブル経済は破綻し、スーパーホースのいなくなった競馬界も一時期の活気を失った。そして僕の生活も大きく様変わりをした。生きがいというものを見つけ、また新たな一歩を歩み始めた。激しい熱に浮かされ、人々が狂喜乱舞していたあの時代。思い起こせば、底なしの空しさを経験し、その中で一頭の名馬に出会えたからこそ、この自分があるのだと今は思える。多くの人々の中にそれぞれの強い思いを残した名馬「オグリキャップ号」は20歳を越した現在、北海道静内町にある牧場で穏やかな余生を送っているという。けれど彼の勇姿は、これからも僕の心のターフの上で永遠に駆け続けるのだ。
2006.3.16 掲載
|



